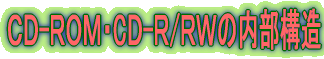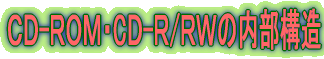CD-ROMやCD-R/RWはどのような構造になっているのでしょうか CD-ROMやCD-R/RWはどのような構造になっているのでしょうか
CD-ROM及び音楽CDの構造
 CD-ROMや音楽CDは記録方式こそ異なりますが、構造的にはまったく同じで、板の断面を見ますと下図のように、表(ラベル)側から順に、保護層(ポリカーボネート) → 反射層(アルミ) → 基板という順で構成されています。 CD-ROMや音楽CDは記録方式こそ異なりますが、構造的にはまったく同じで、板の断面を見ますと下図のように、表(ラベル)側から順に、保護層(ポリカーボネート) → 反射層(アルミ) → 基板という順で構成されています。
基板にはくぼみがあり、これを『ピット』と呼んでいます。又、ピット以外の部分、つまり平面部分を『ランド』と呼んでいます。これらに読取ヘッドからレーザー光をあてると、レーザは反射層で反射し、基盤を通してヘッドに戻ってきます。この時ランド・ピットの境界部と、それ以外とでは反射に変化が現れてきます。そして境界部を『1』、それ以外の部分を『0』のデジタル信号として認識することにより、データを読み取っています。
ちなみにCD-ROMや音楽CDでは、このくぼみ(ピット)を基板樹脂を成形(プレス)することにより作成しています。この方法は同じものを大量に生産する場合に適しています。
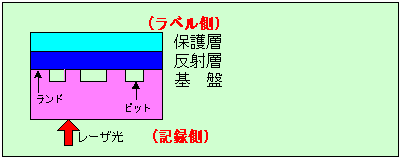
CD-R及びCD-RWの構造
 CD−Rの構造がCD-ROMと異なる点は、反射層と基板の間に有色色素という記録層があることです。CD-ROMがプレスによりピットとランドを作成するのに対し、CD−Rでは有色色素部分に強いレーザ光を当て、これを熱で分解することにより、ランドとピット部を作り出しています。一度熱で分解した有色色素は二度と元に戻すことができません。だからCD-Rは書換えができないという事になります。 CD−Rの構造がCD-ROMと異なる点は、反射層と基板の間に有色色素という記録層があることです。CD-ROMがプレスによりピットとランドを作成するのに対し、CD−Rでは有色色素部分に強いレーザ光を当て、これを熱で分解することにより、ランドとピット部を作り出しています。一度熱で分解した有色色素は二度と元に戻すことができません。だからCD-Rは書換えができないという事になります。
一方CD-RWは有色色素の代わりにアモルファス合金が挟み込まれており、これにレーザ光線をあて結晶状態と非結晶状態(急激に温度を上げ下げすると非結晶、ゆっくり温度を上げ下げすると結晶)を作り出すことにより、ピットとランド部を作りデータの記録をします。又、読むときにはレーザ光線をあて、反射の強弱によりデータの識別をします(結晶状態だと反射が強く、非結晶の場合は反射が弱くなります)。このように熱で結晶・非結晶状態を自由に変化できますのでCD−Rと違い何度(約1000回)でも書換えができます。
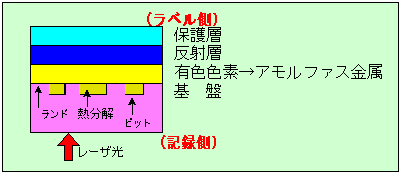
|