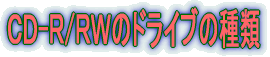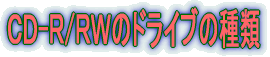CD-R/RWドライブにはどのような種類があるのでしょう CD-R/RWドライブにはどのような種類があるのでしょう
 CD-R/RWドライブをパソコンに接続するには、ドライブとパソコンとのインターフェースが必要となります。一口にインターフェースといっても実に様々な種類ものがありますが、CD-R/RWドライブで使用されている主なものとしては、『ATAPI』『SCSI』『USB』『IEEE1394』等になります。又、内蔵か外付けかによっても種類を分けることができます。従って、CD-R/RWドライブを選択する時には、各人のパソコン環境や好みに合せて適切なインターフェース及び内臓が外付けかを選択する必要があります。ここではこれらのインターフェースの特徴について簡単に説明します。 CD-R/RWドライブをパソコンに接続するには、ドライブとパソコンとのインターフェースが必要となります。一口にインターフェースといっても実に様々な種類ものがありますが、CD-R/RWドライブで使用されている主なものとしては、『ATAPI』『SCSI』『USB』『IEEE1394』等になります。又、内蔵か外付けかによっても種類を分けることができます。従って、CD-R/RWドライブを選択する時には、各人のパソコン環境や好みに合せて適切なインターフェース及び内臓が外付けかを選択する必要があります。ここではこれらのインターフェースの特徴について簡単に説明します。
ATAPI (AT Attachment Packet Interface)
ATAPI(アタピと呼びます)は比較的ドライブの価格が安く、主にディスクトップパソコンの5インチベイに取付る内臓型ドライブ用のインターフェースです。殆どのディスクトップパソコンには内臓ハードディスクを取付けているIDE規格のケーブルが内蔵されており、このケーブルの途中に分岐させて取付けることができます。従って改めてインターフェースを準備する必要がありません。又転送速度も33-66MB/秒と速く、又設置場所を取らず、非常にコストパフォーマンスの高い効率的なインターフェースと言えます。しかし取付方法は本体を分解して取付ける必要があるため、4つのインターフェースの中では一番厄介で、取付の知識が少し必要となります。(この取付け方法については別途後のサイトでご紹介をします)
SCSI (Small Computer System Interface)
SCSI(スカジと呼びます)の歴史は古く、数年前まではインターフェースといえばSCSIが中心で、殆どの周辺機器はこのインターフェースで接続をしていました。SCSI対応のドライブを取付けるには、別途SCSIボード必要で、これを増設ボードに取付ける必要があります。最初にSCSIインターフェースを取付ける時だけは少し面倒ですが、ATAPIに比べると簡単で、ドライブを一台接続すると、2台目以降は簡単で、そのドライブから分岐して、数珠繋ぎで最大8台くらいまでの機器を接続できます。転送速度は10-80MB/秒とATAPIと同じかそれ以上です。
USB (Universal Serial Bus)
USBは比較的新しいインターフェースですが、最近はかなり普及してきています。最大転送速度は1.5MB/秒と低速ですが、取り扱いが非常に簡単で素人向けのインターフェースといえます。ホットプラグといい、電源を入れたままの抜き差しも可能で、電源供給もある程度までならコネクタから供給可能です。最大127台の機器を繋ぐこともでき、物理的な接続方法も非常に簡単で便利です。しかし、転送速度が非常に遅いためハードディスクなどの高速性が要求される装置には適していません。但し、現在IEEE並みの60MB/秒位の高速のUSB2が開発中であり、来年あたりには登場することになっています。今後の主力となるインターフェースです。
IEEE1394 (Institute of Electrical and Electronic
Engineers 1394)
IEEE1394(アイ・トリプル・イー1394と呼びます)は次世代の高速SCSIとしてアップル社が開発したもので、その後IEEE(米国電気電子技術者協会)に、よって標準化されました。最大転送速度が12-50MB/秒で、64台の機器を接続でき、USBと同様ホットプラグ対応で、コネクタからの電源供給ができます。USB
2.0製品がまだ市場にほとんどなく、現在ではもっとも簡単で高速な接続方法といえます。(最新のパソコンには標準でついているようです)
インターフェース |
内臓 |
外付 |
転送速度 |
| ATAPI |
○ |
ー |
33-66MB/秒 |
| SCSI |
○ |
○ |
10-80MB/秒 |
| USB |
ー |
○ |
1.5MB/秒 |
| IEEE1394 |
ー |
○ |
12-50MB/秒 |
|